



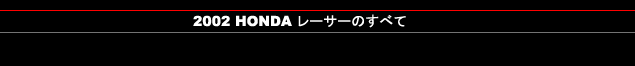
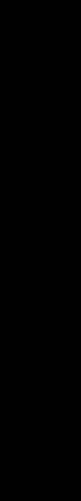
I,can.
|
既成概念完全粉砕、RC211Vの全貌。(1)
三重県、鈴鹿サーキットのバックストレッチ。
スプーンコーナーを立ち上がり、ゆるやかな左カーブとともに約1kmほど続くこのミドルストレートは、鈴鹿サーキットにおいて最高速がマークされるポイントだ。これまで何度このストレートを走ったのか数え切れない。
はじめて走ったのは1988年の暮れ、当時のホンダRS250でだった。それまで筑波と菅生しか走ったことのなかった18歳の俺には強烈なインパクトを持つストレートで「250のバイクってこんなに速いのか」ということを実感した場所でもあった。複合コーナーのスプーン2つめを2速で立ち上がり、思い切り下りながらストレートに入っていく。それまでの関東以北のサーキットではけして感じることが出来なかった様々な「G」を感じ、思うようにバイク操作が出来ないことを知る。ギヤチェンジやストレート姿勢に持っていくことさえままならない。小手先足先だけの峠乗りや原チャリレース技術がまったく通用せず、加速力と遠心力とコースの起伏があらゆる重力引力を増大させて、それまで持っていたスキルすべてを打ち砕く。バイクで走ることによって発生する慣性力の強大さと、その中での自分の無力さを嫌というほど思い知る。自分がレースで愛用していた市販NSR250のSP仕様のバイクよりもはるかに馬力の出ていた市販レーサー、RS250に乗りながら、俺はNSR250のタイムを上回ることが出来なかった。こんな場所でレースをするのかよ、そう愕然としたことを今でもよく覚えている。鈴鹿は、日本では特種なコースだ。
「バックストレッチの登りきったとこあるじゃないですか?あそこは500も浮きましたけど、RCは浮くなんていうもんじゃないくらい持ち上がります」
走行前にHRCの契約GPレーサー、宇川徹はそうアドバイスをくれた。以前ヨシムラのハヤブサに乗るライダーも同じことを言っていたが、俺は鈴鹿でスーパーバイク以上に速いマシンに乗ったことがなかったので、どういうものなのかまるで想像できなかった。スーパーバイクのマシンではどんなに速いものでもそのポイントでフロントが浮き上がることなどなかった。しかしRC211V(以下RC、HRCの連中は皆このマシンをRCと呼んでいた)でこのバックストレッチに差し掛かるまで、例えばデグナー2つめやヘアピン立ち上がりという1速からの加速力の断片を体感しただけで「これはとんでもない ことになるだろうな」というハッキリとした予感があった。その遠雷よりもはるかに輪郭の整った電気的な予感はこれまでけして感じたことがないほど強烈かつ異次元レベルのもので、俺の頭の中には「三重県鈴鹿サーキットでモータージャーナリストが事故死」という三面記事や、カタパルトとかロケット発射台とかの映像が入り乱れた。使用している回転数はマックスの半分にも満たないのにとんでもない事態を予感させる。けして入ってはいけない場所にはじめて入っていくときの高揚と不安、それぞれの度合いがここ最近ではなかったほどに膨らみ、そしてそれが最高潮に達したとき、いよいよスプーンを立ち上がった。頂点に向けてアクセルをひねりはじめる。14000回転強でシフトランプがフラッシュするらしい。すぐに未体験の加速力を感じ、とんでもない激流の中で溺れながらタグボートにしがみついているような気分になった。タコメーターを見ると、たった10000回転だった。
ことになるだろうな」というハッキリとした予感があった。その遠雷よりもはるかに輪郭の整った電気的な予感はこれまでけして感じたことがないほど強烈かつ異次元レベルのもので、俺の頭の中には「三重県鈴鹿サーキットでモータージャーナリストが事故死」という三面記事や、カタパルトとかロケット発射台とかの映像が入り乱れた。使用している回転数はマックスの半分にも満たないのにとんでもない事態を予感させる。けして入ってはいけない場所にはじめて入っていくときの高揚と不安、それぞれの度合いがここ最近ではなかったほどに膨らみ、そしてそれが最高潮に達したとき、いよいよスプーンを立ち上がった。頂点に向けてアクセルをひねりはじめる。14000回転強でシフトランプがフラッシュするらしい。すぐに未体験の加速力を感じ、とんでもない激流の中で溺れながらタグボートにしがみついているような気分になった。タコメーターを見ると、たった10000回転だった。
(この先にあと4000回転もあんのかよ)
とにかく伏せれるだけ伏せ、へばりつけるだけへばりつき、この時点でどうでもよくなったプライドではなく本能で全開にする。梨本圭という人間のパフォーマンス、五感、コントロールレベル、そのすべてを軽々と超えてRCは突き進む。まさしく時間を切り裂く感じ。切裂的時間絶景。それでもまだフラッシュしない。3次元だった鈴鹿サーキットは瞬時に2次元の世界に移り変わりすでに『前後』という感覚しかない。すべてがもみくちゃになった俺自身の外側の世界はRCによってとことんまで鋭利に寸断されていく。しばらくしてようやくグリーンのフラッシュが光った。いるはずのなかった地点に自分がいる。あの信号をもし渡れていたら、あの時もし告白していたら、あの時もし失敗せずに走っていたら。これまでレーサーとしては絶対にタブーとされていたそういうIFの部分に自分が突き進んでいる。それはサーフィンをしているとき、巨大な波からすべり落ちてそのまま海底に引きずり込まれ、そこから激しい海流によってまったく予測外のとんでもない方向へと瞬時に打ち上げられた後の敗北感に似ていた。つまりIFは自分の力で達成されたのではなく、自分以外の強大な力によって強引に成されたということだ。オートシフターでギヤを上げていく。なんと表現していいのかまったくわからない加速が続く。宇川が注意をうながした、ストレートの中腹過ぎ、登りきる地点がすぐそこにある。このまま全開でいけば間違いなく後ろにひっくり返るだろう。5速以上で、ほんの少しの起伏によって、後ろにひっくり返ることが可能な加速力を持つマシン。こんなものを誰が考え、そして作り出そうと決心したのだろうか。そもそも今乗っているこの乗り物は一体なんなのだろう。本当にタイヤは二つしかないのだろうか。
一周目の起伏の上を、全開で通過することが出来なかった。
