



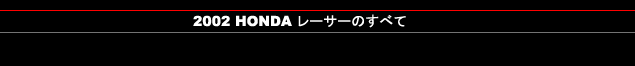
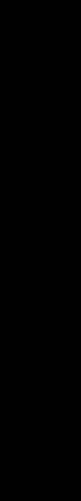
I,can`t.
|
NSR500は遺物か。
こういうたわけたことを言うバイクファンが多いが、それは全世界のオスの究極の性的興奮快楽曲線を過去の遺物だと宣言するに等しい。つまり生命の起源を否定することと同じだ。RCの加速感はとめどなく湧き出る清水のようにどこからでも湧き上がり、そしてそれが鉄砲水のように破壊的な勢いを持っていつまでも続いた。それに対しNSR500の加速はまさしく瞬発的に立ち上がりあっというまに絶頂を迎え、果てる。その絵に描いたような2次曲線はオスの性的興奮快楽曲線とまったく同じカーブを描きつつ、しかしとんでもないスピードで6つの感覚器官の頂点へと向かう。1速視覚、2速聴覚、3速嗅覚、4速味覚、5速皮膚覚、そして6速はシックスセンス、つまり第6感。速度を増すごとにそれぞれの感覚器官が見事なまでにぶっ壊れていき、最終的にはシックスセンスだけでの勝負になる。
10000回転まではまったく隆起をみせない。それが逆に期待と恐怖感を煽る。
誰もいない山奥の野池にフローターで入り、一投目、トップウォータープラグを投げた。ルアーが着水したその余波が静かに池全体に伝播し微小な浮揺がフローターを包む。右手の中にあるアブクラッシック1500から水面下のすべての気配を感じ取る。けして竿先を乱さないように注意しながらほんの少しだけ息をした。吸うのではない。邪気を吐くだけだ。20メートル先に浮く十八番のハードルアーは止まったまま野生の静を演じている。野生の静とは呼吸を大気のうねりに這わすこと。水面から余波のすべてが消えた。いつもは自然の風によってだけ池面の起伏が作り出されるが今日は無風だ。ゆっくりと二回、トゥウィッチする。1553ミリ、短か目の竿は手首と同調しラインで結ばれた先のハードルアーが今度は野生の動を演じた。大気に対する小さな小さな反復。たった二回、右、左と2ストロークだけのウォーキング。ハードルアーはスーッと池面を滑っていき、ほどなくして静と動の境界線を失ったままに止まる。次の瞬間、マグマが大爆発したかのように水面が砕ける。
ハードルアーが大きく弾かれる。それまで演じられた野生は明らかな異物と化し水上を舞う。三度着水する直前、再度水面が爆発した。ハードルアーが姿を消す。よれていたラインは細いガラスのように直線的になり、竿先はこれでもかと弓形に反る。手の中のアブクラッシック1500は悲鳴をあげて糸を吐き出す。フローターがどこかへと運ばれていく。暴力的な手応えは手首だけでなく腕、肩、腰、両足に衝撃を広げる。潮の満ち引きと逆のコミュニケイション。激しい水飛沫が谷間に木霊する。整っていた水面はもう無茶苦茶だ。やがてこのでかいバスは俺に釣り上げられるだろう。そう思うと絶対的な興奮が沈化した。あの瞬間、まったく隆起のない水面が砕けるその一瞬、そのときだけにすべてが詰まっている。
 バックストレッチ。11000回転弱で水面が砕けた。凄まじい排気音が炸裂する。ロックに音楽的なアクセントは存在しない。一定のリズムベースにふりかけ程度のギター、そして無力なボーカルが歌詞という念仏を唱えるだけだ。しかし歌詞が意味を持たない音源には必ず強烈なアクセントが存在する。歌詞のない音源こそが本質的な音楽なのだ。音は意味ではなく、食べ物や飲み物のように自然に音楽が体に入ってくる。前菜のサラダ、薄味のスープ、乾いてニュートラルなパン、そして香辛料の利いた肉や魚、すべてを柔らかく正調するワイン。それらと同じようにアクセントを伴って体に浸透する。人間はアクセントに弱い。アクセントがなければたちどころに飽きてしまう。痩せた女が流行るとデブが栄え、電子メールが流行ると絵葉書が重宝する。大きな起伏を持つ一定ではない加速力は今更ながら魅力的なアクセントだった。ブラックバスを操る神は池面を砕かせる瞬間に一体どんな指揮をとるのか。指揮者がどれだけオーバーハングしてみせてもこのアクセントは演出できない。130Rが近付き景色が第6感に進入したとき乾いたアクセントの断続的な叫びを殺す。そして水面はまた収束に向かう。
バックストレッチ。11000回転弱で水面が砕けた。凄まじい排気音が炸裂する。ロックに音楽的なアクセントは存在しない。一定のリズムベースにふりかけ程度のギター、そして無力なボーカルが歌詞という念仏を唱えるだけだ。しかし歌詞が意味を持たない音源には必ず強烈なアクセントが存在する。歌詞のない音源こそが本質的な音楽なのだ。音は意味ではなく、食べ物や飲み物のように自然に音楽が体に入ってくる。前菜のサラダ、薄味のスープ、乾いてニュートラルなパン、そして香辛料の利いた肉や魚、すべてを柔らかく正調するワイン。それらと同じようにアクセントを伴って体に浸透する。人間はアクセントに弱い。アクセントがなければたちどころに飽きてしまう。痩せた女が流行るとデブが栄え、電子メールが流行ると絵葉書が重宝する。大きな起伏を持つ一定ではない加速力は今更ながら魅力的なアクセントだった。ブラックバスを操る神は池面を砕かせる瞬間に一体どんな指揮をとるのか。指揮者がどれだけオーバーハングしてみせてもこのアクセントは演出できない。130Rが近付き景色が第6感に進入したとき乾いたアクセントの断続的な叫びを殺す。そして水面はまた収束に向かう。
S字が連続する東コース、マシンは必ず右か左かに寝ていてことさら丁寧なアクセレーションが求められる環境下、俺はまともにNSRを走らせることが出来なかった。ホンダワークス各マシンの試乗時間はたった15分だ。鈴鹿サーキットフルコースの場合、5周もすれば終わってしまう。2ストロークの500cc200馬力近いマシンの2速、パワーバンド付近にいながら高荷重のS字を重く重く切り替えしつつ、右手で1ミリ単位の作業を行うことなど現役のワークスライダーでもないのに出来るはずがない。だからS字区間は苦痛そのものだった。いつ水面が割れるのかまったくつかめない。恐ろしくてしょうがない。予定調和のアクセントは下品だが、まったく予測できないアクシデントも好きじゃな い。 その典型的な飛行機事故など絶対に嫌だ。それでもデグナー二つ目では思い切りハイサイドを食らった。アゴが外れそうになるほどの衝撃だった。二年前にもてぎでNSR500に乗ったときは「一家に一台欲しい最高の遊び道具だ」と感じた。可能ならNSRを買ってとっくに失効した筑波サーキットのライセンスを取得し、トランポも買って週末に走りにいきたいと本気で思った。しかし鈴鹿でのNSRはそんなものではなかった。こんなバケモノが一家に一台あったら全員即死だ。ちなみに試乗車は加藤大治郎車で、恐ろしくポジションが小さく、まるで200馬力のNSR50に乗っているような感覚だった。NSR50のポジションで200馬力もあるマシンをまともに操ることなど出来ない。縮こまった体の下で暴発的なパワーを炸裂させるNSR500はハッキリとしたアクセントで俺に言う。
お前は乗るな、死ぬぞ、分かったか。
何かに挑めば簡単にバラバラになって死ぬだろうな、ということをアゴが外れそうなヘルメットの下で理解した。チャレンジする気にまったくなれない。こんなものでどうやってレースをするのだろうか。周りにはこのNSRを「正常進化」と評する人たちがたくさんいた。コイツらマジかよと思う。信じられなかった。このマシンの進化の過程を追うには、もう一度俺自身の免許取得からサーキットを走り出すまで、つまりバイクに関わり始めたときからのプロセスすべてをやり直さなければ意味がないと思った。今までのバイクとの関わり方そのものをすべて変えなければNSR500を解析することなど出来ない。初冬の鈴鹿、路面温度が低く数周で温まるはずのないタイヤ、そして車重が軽いNSRのカーボンブレーキはまったく温まるまでに至らず、恐ろしく止まらなかった。エンブレもないから減速効力的にはRCの半分ほども効いていない感じだ。つまり俺はNSRのまともなブレーキ効力を立ち上げることさえ出来なかったということだ。
「500は難しいです。ホントに難しいですね」
長年このマシンでレースをしてきた宇川徹がそんなことを言っていた。現役のGPレーサーさえ難しいと言うマシンを、たった15分だけ乗ってそのバケモノ特性を「こういうもんだ」などと俺は言えない。そんなことを言うのはスピードへの冒涜であって愚の骨頂以外の何物でもない。
乾いた排気音はストレートできっちりと6つの絶頂を迎え、そして果てる。RCとは加速の感覚がまったく違うが、そのマックス領域でのパワー差というのを厳密に俺自身が捉えているかどうかも著しく疑問だ。RCはどこからでも加速する。パワーバンドを選ばず、開ければその瞬間に前に出て行く。しかしNSRは違う。しっかり回してやらなければ凄まじい駆動力を得ることはできない。それでも一度池面を砕けば、その破壊力はハンパでではない。RCを「NSRよりぜんぜん速い」というジャーナリストもたくさんいたが、俺は500に乗っているとき、ストレートだけでタイミングを合わせてアクセルを開け、前を走るRCを何回も抜いた。つまりどのマシンでも全開にすら出来ていない人がほとんどだということだ。そんな運転レベルでNSRとRCを比較していること事態バカバカしいと思えた。
俺が直線で唯一RCとNSRが決定的に違うと思えたのは、あのバックストレッチの中腹過ぎ、登り切った地点での反応だった。RCは、通常サーキットのストレートで乗る位置(前衛投影面積を減らすためにかなり後ろ気味に座る)でそこを通過すると、6速全開でウイリーして後ろにひっくり返りそうになった。しかしNSRは、ウイリーはするものの全開のままでそこを通過し、やがてフロントタイヤが緩やかに着陸してくれた。そう、まさしく着地ではなく着陸という感覚だった。飛行機のリヤタイヤが地球に接地し、その少しあとにフロントタイヤが着陸するときの感覚。その間数秒、もしくは数十秒でしかないのに、とんでもない地対空距離を走っているという事実。俺にとってはその感触だけが2台のマシンの決定的な絶対動力性能の違いであり、あとの、例えば200馬力近辺での加速力の上下関係を五感で捉えることは出来なかった。シックスセンスで何かを感じ取れる余裕も皆無だ。両方とも無っ茶苦茶にはええ、なんなんだこりゃ、それしかなかった。それが梨本圭の15分間で感じ取れるれることのすべてだった。
RCにはとてつもなく新しい何かを感じたわけだが、NSRには襟を正されるような心持にさせられた。2サイクルの乾いた排気音、瞬発力、その最高峰最速マシンの絶対的な加速力。言うまでもなくこの2002年加藤モデルのNSR500には、フレディ・スペンサーからワイン・ガードナー、ニール・マッケンジーやエディ・ローソン、そしてマイケル・ドゥーハン、アレックスクリビーレ、バレンティーノ・ロッシ、そして伊藤や岡田や宇川まで綿々と続く息吹が盛り込まれている。俺はその過程でレプリカブームという時代に生き、恐らくこの国で一番公道やサーキットで「レーサーを目指す者」が多かった時代を散々謳歌してきた。150馬力近いビッグマシンが日常になった今も「2stこそが俺のバイクの原点」という思いは消えたことがない。俺のバイク歴はまさしくそのレプリカの「‘87NSR250」で始まった。
 数日後、梨本塾に参加する小僧系の若者が自分のNSR250で4度転倒し、最終的にクランクを焼き付かせた。「この近くにバイク屋ないですか?」彼は言う。あることはあるが、こんなもん持っていっても直らないだろう?すると「いえ、頭にきたから捨てていきます。廃車にします」と彼はすがすがしく応えた。なんの迷いもない表情だった。俺は大笑いした。梨本塾に参加し、そこで転倒した直後に「このバイク捨ててきます」と言い放った奴ははじめてだったからだ。なんていさぎのいい19歳なんだと嬉しくなってしまった。彼はけして大金持ちの息子ではない。いつも小銭に悩む普通のティーンエイジだ。
数日後、梨本塾に参加する小僧系の若者が自分のNSR250で4度転倒し、最終的にクランクを焼き付かせた。「この近くにバイク屋ないですか?」彼は言う。あることはあるが、こんなもん持っていっても直らないだろう?すると「いえ、頭にきたから捨てていきます。廃車にします」と彼はすがすがしく応えた。なんの迷いもない表情だった。俺は大笑いした。梨本塾に参加し、そこで転倒した直後に「このバイク捨ててきます」と言い放った奴ははじめてだったからだ。なんていさぎのいい19歳なんだと嬉しくなってしまった。彼はけして大金持ちの息子ではない。いつも小銭に悩む普通のティーンエイジだ。
こういう場合「自分のマシンをなんだと思っているのだ!?直して大事に乗れ!」と即座に激怒するバカな大人がたくさんいる。しかしNSRでバイクをはじめた俺は思う。NSRに乗り、誰よりも速く走る面白さを知り、さらに頂点の頂点を目指すものにとって、どんなに愛着があるものでもバイクは道具でしかないのだ。NSRでしか味わえなかった感覚、抱き得なかった思いというものがある。それを知らない大人が多すぎるだけだ。それを知れば、それを教えてくれたNSRそのものが速く走るための道具でしかないということを思い知る。自分の速度を上げていくためには、けして懐古主義的な愛着心に縛られてはいけない。NSR250とともに時代を生きた人にとって、それは足かせにしかなりえない。レベルダウンして「落ち着いた」などと言い換える老人にはなりたくない。毎日毎日速く走ることだけを執拗に考えつづけたい。
 小僧は塾の帰り、実際に俺の行きつけのバイク屋にNSRを捨てていった。また嬉しくなった俺は、小僧に了解をとり、即日名義変更してそのNSR250を直して自分で乗ることに決めた。500に乗り、何も出来ない出来ないと感じた今の自分が、何でも出来ると思えたNSR250に跨ってまた何かを思い出せたらな、と思った。やっぱりNSRは最高の道具だ。
小僧は塾の帰り、実際に俺の行きつけのバイク屋にNSRを捨てていった。また嬉しくなった俺は、小僧に了解をとり、即日名義変更してそのNSR250を直して自分で乗ることに決めた。500に乗り、何も出来ない出来ないと感じた今の自分が、何でも出来ると思えたNSR250に跨ってまた何かを思い出せたらな、と思った。やっぱりNSRは最高の道具だ。
エッジ度、100点。
結論、NSR500とは?
20世紀最後のレースシーンを常にリードし続けた最高の2サイクルマシン。10000回転以上での炸裂感は市販リッターマシンの比ではない。90年代以降は乗りやすさを追ったとはいえ、それはあくまでレースの世界のスペシャリストにとっての話で素人がまともに走らせられるようなシロモノでもない。かつてのすべてのNSR250ファンの象徴として、有り余るパフォーマンスを未だに誇示し続けている。
